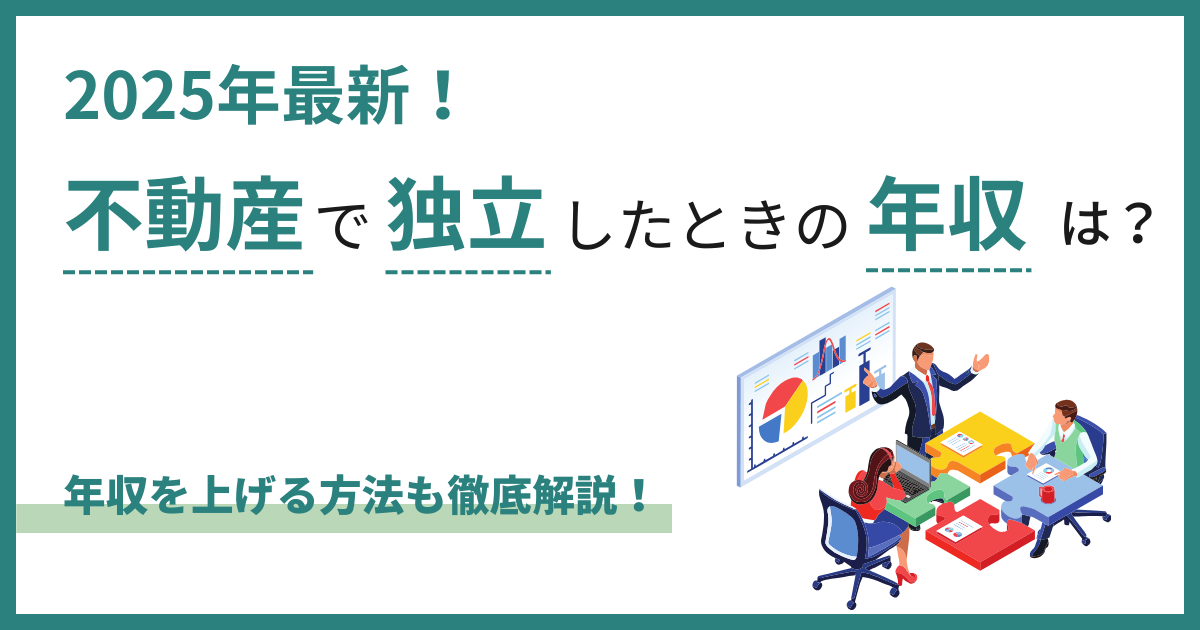
不動産で独立した場合の年収相場は?失敗しない方法や年収を上げる方法も同時に解説
- コラム
FINSTAR AGENT編集部
不動産業界は、成果次第で大きな収入を得られることから、独立を目指す人が多い分野です。実際、1人で開業して年収500万〜1,000万円以上を達成しているケースも珍しくありません。
一方で、「独立したらどれくらい稼げるのか?」「売上を安定させるにはどうすればいいのか?」「年収を伸ばす具体的な方法はあるのか?」といった不安を抱えている方も多いでしょう。
そこで本記事では、不動産で独立した場合の年収相場をはじめ、売上の仕組みや収益源の種類、年収を上げる方法、独立のメリットや注意点を整理して解説します。さらに、必要な資金や資格、開業までの流れも紹介するので、独立を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産業で独立する場合の方法や失敗リスクについては、以下の記事で網羅的にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産業で独立するには?年収・開業方法・リスクについても解説
目次
不動産で独立した場合の年収相場

不動産業で独立した場合、年収は人によって大きく差が出ます。売買仲介をメインにすれば1件あたりの手数料が高く、短期間で1,000万円以上の年収を得ることも可能です。一方で、賃貸や管理を中心にすれば単価は低いものの、契約数を積み重ねて安定収入を実現できます。独立後の年収はビジネスモデルや戦略の違いによって大きく変動します。
ここでは、不動産業で独立した場合の年収相場と年収の変動要因について解説します。
年収相場は300万円から2,000万円までと幅広い
不動産業で独立した場合の年収は、選ぶ事業モデルや営業力によって大きく変動します。平均的には会社員より高水準を狙える一方、独立者の分布は広く、年収300万円台から2,000万円超まで幅広いのが特徴です。
不動産流通推進センターの統計では、資本金1,000万円未満の小規模不動産業者における従業員1人あたりの年間売上は約1,553万円とされています。【不動産流通推進センター「不動産業統計集2023」から試算】。経費率をおおよそ50%と仮定すると、実質的な利益(手残り)は770万円前後と推定され、規模が小さい事業でも高収益を上げられる可能性があることが分かります。
参考:不動産流通推進センター
不動産で独立した場合の年収は、年収300万円台からスタートするケースもあれば、営業力や事業戦略次第で年収1,000万円超、さらには2,000万円超も現実的に目指せるという、幅の広い相場となっています。
年収が大きく変動する要因とは
不動産で独立した場合、同じ規模や経験でも年収に大きな差が出ます。その理由は、収益に直結する要素が多岐にわたり、それぞれの状況によって結果が左右されるからです。特に影響が大きいのは以下の5点です。
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 扱う物件の種類 | 売買仲介は1件あたりの手数料が高額である一方で、賃貸仲介は単価が低いが件数を積み重ねやすい。 |
| 地域性(エリアの特性) | 都心部は物件価格・取引数が多く高収益を狙いやすい。地方は単価が低め。 |
| 営業力・クロージングスキル | 「この人から契約したい」と思わせる信頼構築力や提案力があるかどうか。 |
| 顧客ネットワーク | 独立前に築いた人脈や紹介ルート、法人・過去顧客との関係性の有無。 |
| 広告戦略・集客チャネル | ポータルサイト、SNS、SEO、紹介など、多様な集客手段を持っているかどうか。 |
これらの要素をどう組み合わせるかによって、独立後の年収は大きく変わります。事前に強みを磨き、戦略的に取り組めば、安定した高収入を実現することは十分に可能です。
不動産で独立した場合の収益源

不動産業で独立した場合、収入の柱は仲介手数料だけではありません。売買や賃貸の仲介を中心にしつつも、自社物件の賃料収入やリフォーム・リノベーションの提案、さらには投資家向けのサポート業務など、複数の収益源を組み合わせることで事業の安定性と年収アップを図ることが可能です。
ここでは、不動産独立で代表的な収益源を整理して解説します。
売買仲介手数料
不動産業界での独立後の収益源として最も大きな柱となるのが、売買仲介手数料です。売買仲介は1件あたりの単価が高く、成約数が少なくても大きな収益につながるのが特徴です。
仲介手数料の上限は「物件価格の3%+6万円(税別)」と法律で定められています。例えば3,000万円の住宅を仲介した場合、受け取れる報酬は約96万円です。これは一般的なサラリーマンの月給を大きく上回る金額であり、短期間でまとまった収入を得られる可能性を示しています。
また、都市部の高額物件や商業用不動産を扱えば、1件で数百万円規模の手数料収入となるケースもあります。そのため、売買仲介をメインに据えると、年収1,000万円超えを狙いやすいモデルとなります。
一方で、売買仲介は景気や市場動向の影響を強く受けるため、契約が集中する時期と少ない時期の差が大きいのも事実です。安定的に成約を重ねられる営業力や、紹介ルートを確保しておきましょう。
賃貸仲介手数料
不動産業界の独立において、賃貸仲介手数料も重要な収益源のひとつです。売買に比べると1件あたりの単価は低いものの、契約件数を積み重ねやすい点が大きな特徴です。
賃貸仲介の手数料は、家賃1か月分(税別)が上限と定められています。例えば家賃8万円の物件を仲介した場合、1件あたりの収入は約8万円です。売買のように1件で大きな金額にはなりにくいですが、繁忙期には1人で月10件以上の契約をまとめることも可能で、件数の積み重ねによって安定的な収益を得やすい分野です。
さらに、賃貸仲介は売買に比べて需要が安定しており、景気の影響を受けにくいのも強みです。学生や単身者の引っ越し需要、法人の転勤者向け物件など、年間を通じて一定のニーズが存在します。加えて、契約に伴う更新料や管理契約と結びつければ、ストック型の収益基盤を築くことも可能です。
ただし、競合が多いエリアでは価格競争に巻き込まれやすいため、自社の強みを明確に打ち出すことが収益安定化のポイントになります。
不動産売却による売却益
不動産独立後の収益源として、自社で保有する物件の売却益も挙げられます。これは、仲介ではなく「仕入れて所有した物件を売却する」ことで利益を得るビジネスモデルです。
例えば、中古マンションや戸建を相場より割安で仕入れ、リフォームやリノベーションを行ったうえで再販すれば、数百万円規模の利益を得られるケースもあります。仲介手数料収入に比べると一発の利益が大きく、資金力や市場を見る目があれば短期間で大きな収益を上げることが可能です。
ただし、売却益モデルにはリスクも伴います。仕入れ価格が高すぎたり、市場動向が悪化した場合は、思うように売れず在庫を抱えてしまうリスクがあります。また、購入資金の調達やリフォーム費用の先行投資が必要となるため、資金繰りやリスク管理のスキルが不可欠です。
成功している独立事業者の多くは、仲介収入をベースにしつつ、余力資金を活用して物件の売買を組み合わせることで、収益の幅を広げています。
その他の収益源
不動産で独立した場合、売買や賃貸仲介に加えて複数の収益源を確保することで、事業の安定性を高めることができます。代表的なものは次のとおりです。
| 収益源 | 内容 |
|---|---|
| 自社物件の賃料 | 事務所や住居用の不動産を自社で保有し、賃貸として貸し出すことで安定収入を得る。サブリースやシェアハウス運営も可能。 |
| リフォーム・リノベーション提案 | 仲介顧客に工事を提案し、提携業者から紹介料を得る。顧客満足度向上と追加収益を両立できる。 |
| 不動産投資関連のサポート | 投資用物件の紹介や管理・運用の助言を行い、報酬を得る。投資家層を対象に長期契約を築きやすい。 |
これらの収益源を仲介業務と並行して取り入れることで、売上の波を緩和し、長期的に安定した経営を実現できます。特に独立初期は、単発の売買収入に頼らず、継続収入を確保できる仕組みづくりが重要です。
不動産で独立後に年収を上げる方法

独立して安定的に収入を得るだけでなく、さらに年収を高めるためには「どのように差別化するか」「どうやって集客するか」が重要になります。営業力や人脈だけに頼るのではなく、専門性の確立や効率的なマーケティング、不動産エージェント制度の活用など、戦略的な取り組みが必要です。
ここでは、不動産で独立後に年収を上げるための具体的な4つの方法を解説します。
差別化できる専門性やブランド作り
不動産で独立後に年収を高めるためには、まず他社と差別化できる専門性やブランドを築くことが欠かせません。数多くの不動産会社が存在する中で、ただ物件を紹介するだけでは埋もれてしまい、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。
例えば、以下のような差別化を作り出す必要があります。
- 特定エリアに特化して情報量で優位性を持つ
- 投資用不動産や法人向けテナントなど、ニッチな分野に強みを持つ
- オンライン内見やSNS活用など、デジタル施策でスピーディーに対応できる
独自の価値を打ち出せば、「この分野ならこの人に任せたい」と顧客から指名されやすくなります。
ブランドが確立できれば、紹介やリピートが増え、安定的に契約を獲得できるため、結果として年収アップにつながります。
効率的なマーケティング
独立後に安定して案件を獲得し、年収を伸ばすには効率的なマーケティング戦略が欠かせません。営業力だけに頼るのではなく、集客の仕組みを整えておくことで、契約件数を安定させることができます。
代表的な施策を以下に整理しました。
| 施策 | 内容・特徴 |
|---|---|
| 不動産ポータルサイトへの掲載 | SUUMOやホームズなど主要サイトに物件を掲載し、幅広い層からの問い合わせを獲得できる |
| SEO対策や自社サイトの運用 | 地域名や物件種別で検索されやすい記事を作成し、オンラインからの安定集客を実現する |
| SNSの活用 | InstagramやYouTubeで物件紹介や顧客事例を発信し、潜在顧客との接点を増やす |
| CRMの導入 | 顧客管理ツールで問い合わせや既存顧客のフォローを効率化し、成約率を高める |
これらを組み合わせることで、少ない労力で安定した案件獲得を実現できます。特に独立初期は広告コストを最小限にしつつ成果を出す工夫が重要です。
人脈(コネクション)
不動産業で独立後に年収を伸ばすためには、人脈(コネクション)の有無が大きな分かれ道になります。独立直後は知名度や集客基盤が整っていないため、紹介や口コミが売上の大部分を占めるケースも少なくありません。
また、顧客ネットワークの人脈だけではなく、以下のような人脈を持つことで、スタート時の売上は大きく変わってきます。
| コネクション先 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 過去の顧客 | 独立後も継続的な相談や紹介を受けられる |
| 士業(弁護士・税理士・司法書士など) | 不動産取引に伴う専門手続きで協力体制を築ける |
| 建築業者・工務店 | 住宅購入やリフォーム案件と連動した紹介を得られる |
| 金融機関 | 融資やローン相談を通じた顧客紹介が期待できる |
| 同業者や他業界の営業パートナー | 情報交換や案件のシェアで営業機会を拡大できる |
広告費をかけずに案件を獲得できるだけでなく、信頼性の高い顧客層とつながることが可能になります。逆に人脈が乏しいと集客のために広告出稿に頼る必要があり、初期コストが増えてしまうため注意が必要です。
不動産エージェントの活用
独立後に年収を効率的に伸ばす方法として、近年注目されているのが不動産エージェント制度の活用です。従来の完全独立型と異なり、フリーランスとして活動しながら案件紹介やバックオフィスの支援を受けられる仕組みが整っています。
不動産エージェント活用のメリットは次のとおりです。
- 事務所や人員を抱える必要がなく、低コストでスタートできる
- 案件紹介や営業ツールの提供により、営業に集中できる
- 契約事務や重要事項説明などのサポートが受けられる
- 研修やコミュニティを通じてスキルアップできる
- 成果に応じて取り分が大きく、努力が収入に直結しやすい
特に独立初期は「集客の不安」や「事務負担」が大きな課題となりますが、エージェント制度を利用すれば、リスクを抑えつつ営業活動に専念できる点がメリットです。未経験者や人脈が限られている人でも成果を出しやすい仕組みといえるでしょう。
不動産営業の新しいスタイルを提案
不動産業界で独立したときの年収以外のメリット

不動産で独立するメリットは「高い年収の可能性」だけではありません。収入以外にも、会社員では得られない自由度や事業の柔軟性といった大きなメリットがあります。特に独立を考える段階では、金銭面だけでなくライフスタイルや経営の自由度を重視する人も多いでしょう。
ここでは、年収以外に得られる代表的なメリットを解説します。
自由度が高い
不動産で独立したときの大きなメリットのひとつが、働き方や意思決定の自由度が高いことです。会社員のように勤務時間や営業方針に縛られることなく、自分のペースで事業を進められます。
スケジュールは自ら調整できるため、生活スタイルに合わせた働き方が可能です。また、取り扱う物件や顧客層も自由に選べるため、自分の得意分野を伸ばしながら事業を展開できます。さらに、経営方針や広告戦略も自ら決定できるため、状況に応じて迅速に方針を転換できる点も独立ならではの強みです。
近年はリモート内見やオンライン契約も普及しており、場所や時間の制約を減らす環境が整ってきています。こうした柔軟な働き方は、収入面だけでなく仕事に対する満足度を高める大きな要素となります。
小資本で始められる
不動産での独立は、他業種に比べて小資本で開業できる点も大きな魅力です。飲食業や小売業のように多額の仕入れや在庫管理が不要なため、初期投資を大幅に抑えてスタートできます。
開業に必要な主な費用は、事務所の賃料や宅建業免許の申請費用、保証協会への加入費用などに限られます。一般的には50万〜200万円程度の資金で開業可能とされ、比較的ハードルが低いのが特徴です。
また、在庫を持たないビジネスモデルであるため、資金繰りのリスクも小さく抑えられます。ポータルサイト掲載やWeb集客を活用すれば、広告費も必要最低限にとどめつつ営業活動を進めることが可能です。小規模から始めて徐々に規模を拡大していける点も、不動産独立の強みといえるでしょう。
不動産で独立する場合の注意点

不動産業で独立することには大きな可能性がありますが、同時に注意すべき点も少なくありません。
ここでは、独立に伴う注意点を解説します。
独立する前より業務が多い
不動産で独立すると、会社員時代には分担されていた業務をすべて自分で担う必要があります。営業や物件案内だけでなく、幅広いタスクを並行して進めなければなりません。
主な業務は次のとおりです。
- 広告出稿やWeb集客の運用
- 顧客管理や問い合わせ対応
- 契約書類の作成や重要事項説明
- 会計処理や税務申告
- 法務対応やトラブル処理
当初はすべてを自分で経験することで経営スキルが身につく一方、業務量が多いため負担が大きくなりやすいのも事実です。税理士や行政書士、Web制作会社・不動産エージェントなど、外部の専門家を活用することで、リスクを減らし安定経営につなげられます。
独立初期は年収が安定しない
不動産で独立した直後は、顧客基盤や集客の仕組みが整っていないため、収入が大きく不安定になりやすいのが現実です。会社員時代には企業の知名度や広告枠、紹介ネットワークに支えられて契約を獲得できていたとしても、独立後はすべてを自力で築く必要があります。そのため、契約件数が少なく、数か月間ほとんど収入が得られないケースも珍しくありません。
また、不動産市場には繁忙期と閑散期があり、季節や景気の影響によって成約数が左右されます。安定的に収入を得るためには、複数の収益源を持ち、資金的な余裕を確保したうえで開業することが必要です。特に半年分程度の運転資金を準備しておくと、契約が取れない時期を乗り越えやすくなります。
不動産業での独立に必要な資金・資格・準備

不動産で独立するには、営業力や人脈だけでなく、法律で定められた資格や免許、さらに事務所開設のための資金など、具体的な準備が欠かせません。必要な要件を満たしていなければ宅建業としての営業はできないため、開業前に計画的に整えておくことが重要です。
ここでは、不動産で独立するために押さえておきたい準備事項を解説します。
初期費用とランニングコストの目安
不動産で独立する際には、まず開業に必要な初期費用と、事業を継続するためのランニングコストを把握しておくことが重要です。目安としては、初期費用は50万〜200万円程度、その後の毎月の運営費用は規模や営業スタイルによって変動します。
主な費用項目は以下のとおりです。
- 事務所関連費用(賃料・保証金・内装費など)
- 宅建業免許の申請費用(個人・法人で異なる)
- 保証協会への加入費(約60万円〜、分割払いも可能)
- 広報・営業ツール費用(名刺・パンフレット・Webサイト制作など)
- 広告・集客費用(ポータルサイト掲載料やSNS広告費)
- 通信費・水道光熱費など日常的な運営コスト
- 会計・法務・ITサポートなど外注費
- 車両維持費や交通費
初期費用だけでなく、毎月のランニングコストを事前に試算し、売上目標と照らし合わせた事業計画を立てることが安定経営の第一歩です。資金に余裕を持たせることで、開業初期に契約が少ない時期でも事業を継続しやすくなります。
独立に必要な資格
不動産で独立するには、法律で定められた資格や免許を整えておく必要があります。特に欠かせないのが宅地建物取引士(宅建士)と宅地建物取引業免許(宅建業免許)です。
宅建士は、不動産売買や賃貸契約の重要事項説明を行える唯一の国家資格であり、事務所には従業員5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を配置しなければなりません。自分が資格を持っていない場合は、資格者を雇用するか、共同経営者として迎える必要があります。
加えて、宅建業を営むには宅建業免許が必要です。営業所が1都道府県内にある場合は「都道府県知事免許」、複数の都道府県にまたがる場合は「国土交通大臣免許」となります。申請には事務所の確保、専任宅建士の配置、資金要件の充足などが求められます。
このほかにも、業態によって役立つ資格があります。賃貸不動産経営管理士や管理業務主任者は管理物件を扱う場合に有利であり、ファイナンシャルプランナー(FP)は住宅ローンや資産形成の相談で信頼性を高められます。
宅建士を中心に、業務内容に合わせてプラスαの資格を備えることで、顧客からの信頼度が上がり、競合との差別化にもつながります。
開業までの流れと期間の目安
不動産で独立するには、資格や免許の取得だけでなく、事務所設置や資金準備など複数のステップを踏む必要があります。流れを把握して計画的に進めることで、スムーズに開業を実現できます。
一般的な流れは以下のとおりです。
- 経営形態を決める(個人事業主か法人か)
- 開業資金と半年分程度の運転資金を準備する
- 専任の宅地建物取引士を設置する
- 事務所を確保し、専用スペースや看板を整える
- 宅建業免許を申請する(都道府県知事免許または国土交通大臣免許)
- 保証協会への加入や必要書類の提出を行う
- 名刺やホームページを用意し、広告・集客準備を進める
全体の期間は3〜6か月程度が目安です。資格取得や法人設立の有無によって変動するため、余裕を持って計画することが大切です。
不動産で独立するために方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
不動産業で独立するには?年収・開業方法・リスクについても解説
不動産業で独立するなら不動産エージェント「FINSTAR AGENT」

独立後に安定した収入を得たい、あるいは効率的に年収を伸ばしたいと考えるなら、不動産エージェント制度の活用は有力な選択肢です。従来の完全独立型に比べ、初期投資や運営コストを抑えながら、営業活動に集中できる環境を得られる点が大きな特徴です。
エージェント型は、独立と会社所属の中間に位置づけられる働き方です。案件紹介や営業ツール、契約事務のサポートを受けられるため、集客やバックオフィス業務の負担を軽減しながら成果を出すことが可能です。これにより、早い段階から売上を確保しやすくなり、年収の安定化や向上につながります。
さらに、報酬体系も従来の雇用型営業職に比べて高い取り分が設定されているケースが多く、努力がそのまま収入に直結する仕組みが整っています。実力次第では、短期間で年収1,000万円を超えることも十分に目指せます。
なかでも「FINSTAR AGENT」のようなサービスでは、案件紹介や契約実務のサポートに加え、営業・マーケティングの仕組み化支援やコミュニティ運営といったサポートも提供されています。独立直後の不安定な時期を乗り越えるうえで心強い存在となり、安定した収入基盤を築く近道となるでしょう。
不動産営業の新しいスタイルを提案
まとめ
不動産業の独立は、自由度が高く、成果次第で高収入を狙えるメリットがあります。しかし同時に、営業・集客・契約といった業務をすべて自分で担う必要があり、準備不足や判断ミスは失敗に直結します。成功のためには、十分な情報収集と綿密な戦略が欠かせません。
特に営業に不安を抱える方や人脈が限られている方には、エージェント型独立が有効な選択肢となります。FINSTARのようなエージェント支援サービスを利用すれば、初期費用を抑えて独立しやすく、契約や顧客紹介などのサポートを受けながら安定的に事業を進められます。
「FINSTAR AGENT」では、未経験者でも安心して活動できる体制が整っており、エージェントの報酬最大化を実現する仕組みも用意されています。さらに、横のつながりを生むコミュニティや定期的な業務サポートもあり、一人で悩まずに独立を進められるのが大きな強みです。
不動産業で独立を検討している方は、まずはFINSTAR AGENTの説明会に参加してみてください。
